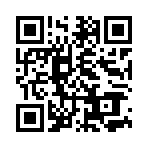2006年08月04日
◇黒鯛記◇ 第2回【落とし込み、前うち】
まだ、釣り雑誌もあまりないころの話。
釣具店で、釣りサンデーという週刊誌を立ち読みする。
落とし込み、前うちという釣りが紹介されていた。
立ち読みで、大まかな知識を仕入れた後、気になって波止や護岸に繰り出してみた。
案の定、誰もそんな釣りはしていない。
常連に話を聞いても、誰もそんな釣りは知らない。
釣具店に舞い戻って、若い店員に聞いてみるとあやふやな答えが返ってくる。
こいつぁ知らないな。
店長に聞いてみると、さすがに猛者だけあって、知っていた。
大阪、名古屋の釣りじゃね。あと東京湾のほうでも、やっとるね。
広島の人も、めったにおらんけど、やっとる人間もおるけどね。
店長にやり方を確認して、仕掛けをそろえた。
竿は専用のものが分からなかったので、ダイワの瀬戸内1.5号を流用。
タイコリールは、店長に取り寄せてもらい、ナイロンの道糸を巻き込む。
肝心の目印は、完成品がなく、自作するしかないが、釣りサンデーの説明じゃぁ良くわからない。
東京湾で主流だという、目印のない落とし込みなら取り合えずできそうだ。
そんなこんなで2日がかりで仕掛けを完成させた。
早速、近所の防波堤へと出かける。
誰もやっていない釣りだ。
結果がどうなろうと知ったことではない。
広島でもホンの数人しかやっていないだろうこの釣り。
しばし優越感に浸りながら黙々と仕掛けを落としていく。
餌は店長おすすめの石蟹と名前をよく知らない殻の柔らかい蟹。
壁際を凝視すると、手のひらサイズのチヌが群れていた。
だが、悲しいことにどのチヌも反応しない。
上手くは行かないのか?
先ほどまでのわくわくした気持ちはどこかへ消し飛び、焦りが出てくる。
この日、チヌが餌に食いつくことはなかった。
別の日、同じように餌を買って防波堤へ。
落とし込みは防波堤でするものだという情報だけが頼りである。
防波堤へと続く道。
ふと見ると、砂浜に岩が点在する場所にチヌがいる。
見えているチヌは釣れないと言うが、どうせこの日も期待は薄い。
本格的に釣りを始める前に、半ばやけくそになって岩陰めがけて仕掛けを振り込む。
5m位は飛んだだろうか?
しばらく待っていると仕掛けが引っ掛かってしまったようだ。
これは切るしかないか?
そんなことを考えていると、ふと引っ掛かった仕掛けが外れた。
再び繰り返すと、同じように引っ掛かる。
馬鹿馬鹿しいことだが、よく考えれば生きの良い蟹がいちいち岩にしがみつき、それを根掛かりと勘違いしてい
たというわけである。
不意に歓喜の時は訪れる。
何と見えていた小チヌがついに餌に食いついたのだ。
この出来事は一生忘れられない。
今では当たり前のことでも当時は意外過ぎることだったのだ。
この日、防波堤でも当たりがでた。
落として落として、最終的に底に蟹がしがみつく。
それを引きはがした時に必ず当たりがきてチヌが釣れてくるのだ。
確かに大きなチヌではない。
しかし、これをやっているのが、多分この地域では自分一人だという勝手な思いこみが喜びを倍増させている
ことは間違いない。
この方法が分かってからは、大きなおもりを付けて蟹を一気に底まで落とし込む方法を身につけた。
中層を無視して、底で蟹を動かすと面白いように良型のチヌが釣れるようになった。
石にしがみついた蟹を無理矢理はがし、再び落とし込む時に必ず当たりがでる。
敷石さえあれば水深は関係なくできてしまうというのがメリットであり、あらゆる場所がフィールドとなった。
この釣りはハードな釣りであった。
バイクに乗って波止から波止へ。
そして、護岸から護岸へ。
真夏の陽に照らされてダウンしてしまうことも多くなり、次第に無理をしないようになった。
こんなことをしていたら、いつか死んでしまうかもしれない。
自分の中で、何かが終わりを告げた。
釣具店で、釣りサンデーという週刊誌を立ち読みする。
落とし込み、前うちという釣りが紹介されていた。
立ち読みで、大まかな知識を仕入れた後、気になって波止や護岸に繰り出してみた。
案の定、誰もそんな釣りはしていない。
常連に話を聞いても、誰もそんな釣りは知らない。
釣具店に舞い戻って、若い店員に聞いてみるとあやふやな答えが返ってくる。
こいつぁ知らないな。
店長に聞いてみると、さすがに猛者だけあって、知っていた。
大阪、名古屋の釣りじゃね。あと東京湾のほうでも、やっとるね。
広島の人も、めったにおらんけど、やっとる人間もおるけどね。
店長にやり方を確認して、仕掛けをそろえた。
竿は専用のものが分からなかったので、ダイワの瀬戸内1.5号を流用。
タイコリールは、店長に取り寄せてもらい、ナイロンの道糸を巻き込む。
肝心の目印は、完成品がなく、自作するしかないが、釣りサンデーの説明じゃぁ良くわからない。
東京湾で主流だという、目印のない落とし込みなら取り合えずできそうだ。
そんなこんなで2日がかりで仕掛けを完成させた。
早速、近所の防波堤へと出かける。
誰もやっていない釣りだ。
結果がどうなろうと知ったことではない。
広島でもホンの数人しかやっていないだろうこの釣り。
しばし優越感に浸りながら黙々と仕掛けを落としていく。
餌は店長おすすめの石蟹と名前をよく知らない殻の柔らかい蟹。
壁際を凝視すると、手のひらサイズのチヌが群れていた。
だが、悲しいことにどのチヌも反応しない。
上手くは行かないのか?
先ほどまでのわくわくした気持ちはどこかへ消し飛び、焦りが出てくる。
この日、チヌが餌に食いつくことはなかった。
別の日、同じように餌を買って防波堤へ。
落とし込みは防波堤でするものだという情報だけが頼りである。
防波堤へと続く道。
ふと見ると、砂浜に岩が点在する場所にチヌがいる。
見えているチヌは釣れないと言うが、どうせこの日も期待は薄い。
本格的に釣りを始める前に、半ばやけくそになって岩陰めがけて仕掛けを振り込む。
5m位は飛んだだろうか?
しばらく待っていると仕掛けが引っ掛かってしまったようだ。
これは切るしかないか?
そんなことを考えていると、ふと引っ掛かった仕掛けが外れた。
再び繰り返すと、同じように引っ掛かる。
馬鹿馬鹿しいことだが、よく考えれば生きの良い蟹がいちいち岩にしがみつき、それを根掛かりと勘違いしてい
たというわけである。
不意に歓喜の時は訪れる。
何と見えていた小チヌがついに餌に食いついたのだ。
この出来事は一生忘れられない。
今では当たり前のことでも当時は意外過ぎることだったのだ。
この日、防波堤でも当たりがでた。
落として落として、最終的に底に蟹がしがみつく。
それを引きはがした時に必ず当たりがきてチヌが釣れてくるのだ。
確かに大きなチヌではない。
しかし、これをやっているのが、多分この地域では自分一人だという勝手な思いこみが喜びを倍増させている
ことは間違いない。
この方法が分かってからは、大きなおもりを付けて蟹を一気に底まで落とし込む方法を身につけた。
中層を無視して、底で蟹を動かすと面白いように良型のチヌが釣れるようになった。
石にしがみついた蟹を無理矢理はがし、再び落とし込む時に必ず当たりがでる。
敷石さえあれば水深は関係なくできてしまうというのがメリットであり、あらゆる場所がフィールドとなった。
この釣りはハードな釣りであった。
バイクに乗って波止から波止へ。
そして、護岸から護岸へ。
真夏の陽に照らされてダウンしてしまうことも多くなり、次第に無理をしないようになった。
こんなことをしていたら、いつか死んでしまうかもしれない。
自分の中で、何かが終わりを告げた。
Posted by te20 at 09:21│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。